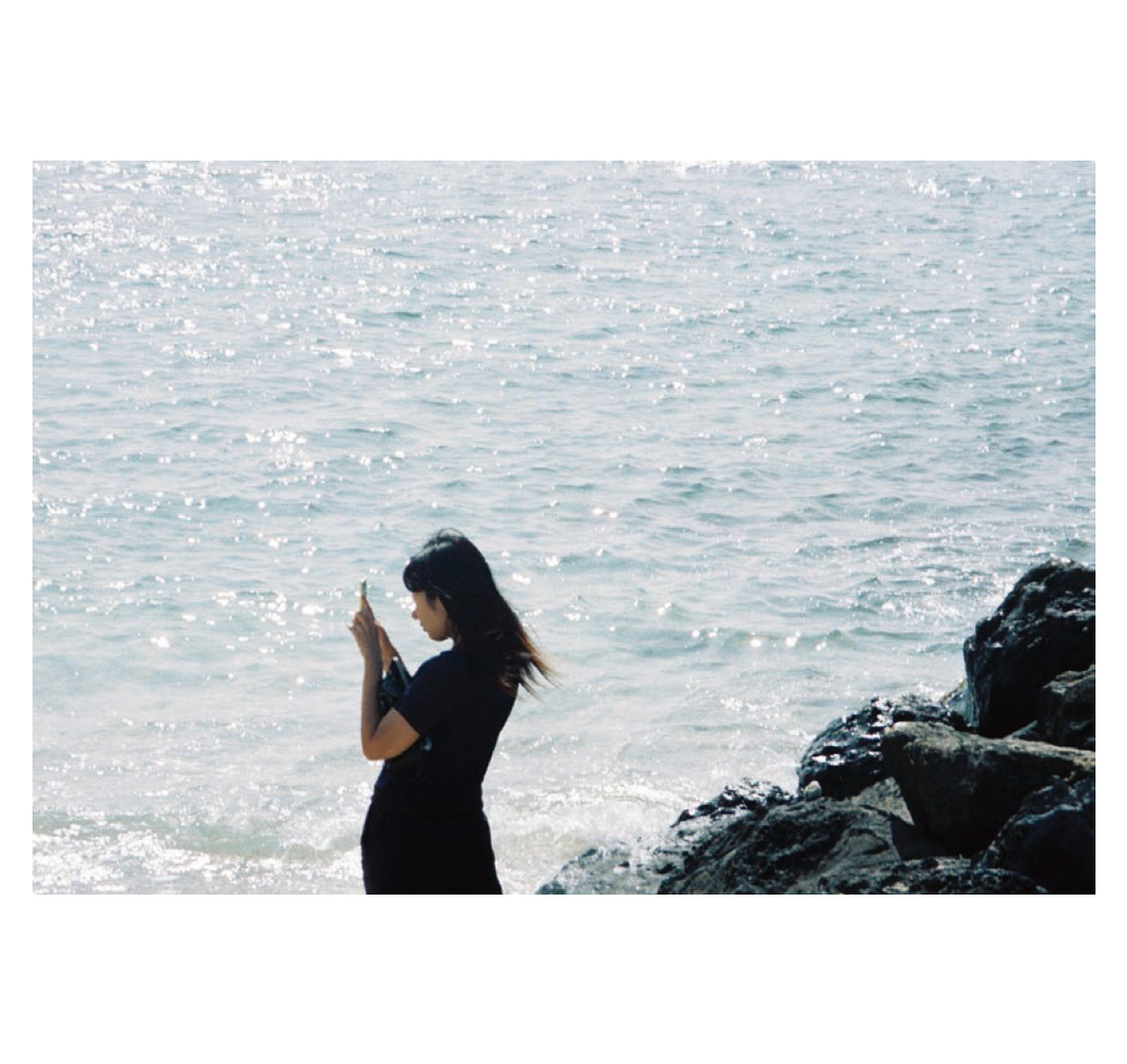2020年12月8日

50歳になってみたら、なんということはない、想像以上の清々しさと、自由な気持ちと、静かな意欲と、「どれにしようかな」などとメニュー表を眺めるあの時間のような色のない気分がやってきた。想像していたよりも、若いのである。気分も肉体も若い。そして新鮮な気分なのです。人によっては孫がいるなんてかたもいるのだろうが、うちにいるちいさいひとたちといえば、猫と犬と、近所にはその犬がうんだ犬なのであって、仕事も25年間本ばかりつくっているのであり、変化がない。大学生の文化祭を大人になってもやっているようなところがどこかある。とうぜん、ある部分が若いままになるのかもしれない。もともとからだがむちゃんこ弱いせいで、あれこれ健康法を続けることとなり、結果、この歳になっていちばん健康状態もよい。82歳になる父に、「わたしが生まれたとき、この娘が50歳になるなんて思った?」と聞いたら、思わなかったという。まあ、そうですよね。父はわたしが生まれた直後に母に「ありがとう」とだけちいさくいったと亡き母から聞いたが、今年もその両親初の娘が生まれた地(岐阜市金宝町1丁目)の目と鼻の先で、みずから誕生日会を催した(近年誕生日は、祝ってもらうというより、身近な人に感謝する日に変えた)。その日も特別に、お給仕係をさせていただき、1770年から続く老舗ワイナリーのビオのワインを注いだり、熱々の菊芋のポタージュだったり、白子のパイをテーブルに運んだりした。シェフは少し前に大怪我をされていたが、そのせいなのか、味が変容し進化していた。繊細に、軽くなり、いうなればアセンションしていた。本当に驚いた。その店とも誕生日が近いのも奇遇なことだと思う。翌日は、9歳になったばかりの友人が、(わたしには9歳から87歳の友人までがいるのです)わたしに誕生日の食事をつくってくれるという。人参のポタージュスープからはじまってオーブン料理、オレンジのゼリーまで続いた。なんという僥倖。子どもがつくる料理というのは、本当に特別な味がすると思う。淡くて、少し天上の味がする。天国で食べるみたいな味。羽がはえたような味といったらいいでしょうか。12月のぽかぽか陽気のなか、うとうとと眠くなってしまった。そのまま、子どもらに見守られて幸福のなか、死んでしまうんじゃないかと思った。自宅にはたくさんの花が飾られていて、特別な気持ちがする。ある意味ではそれまでの自分が死んだのだとも思う。葬いの花とさえとれる。どうしても、何か、あたらしいことをはじめなければならないような気持ちにもなっている。
2020年12月3日

もうすぐグレイトコンジャンクションだそうである。昨年、2020年版の日めくりカレンダーを制作中にこのことを知った。木星と土星の20年ぶりの会合。土の時代からいよいよ風の時代となる。何百年に1度とか何万年に1度とか、地球は、そんな大転換期なんだそうだ。12月に入って、もうその状態に入っている感覚もある。おなかの奥と、ハートの奥と、松果体の奥に、確かな目があった、ということに気づくような感じ。そこから静かに世界全体を感じている感覚。そうやっていると、足の裏にも、手の平にも観察する目があるような感覚がうまれて、もう全方位、見渡せるような感覚になることもある。いずれにしても、ざわざわする、というようなものではない。もう肚くくりましたわ、というようなきわきわ感が12月に入ってひしひしと感じられる。わたし、観て、観て、観ています、という感覚。実際、まやかしの自分を自分などと勘違いしていたことからも多くの人が解放されつつある。たくさんの傷や悲しみや憤りがおもてに出て飛び立ちつつある。鬼は表出し、いやされ、次々と滅されている。太陽で生きると決める人がひとりふたりと続いている。自分のことは自分でする。消費ではなくて生産する。正しいではなくたのしいを選ぶ。すべて100%自分の責任であることを受け入れる。自分の責任で選び行動する。神はすべてをお見通しだ。その神がひとりひとりに内在していることに、人々がきづきはじめている。そうしていよいよ世界に、個人個人がやりたいことをやって、でもまわりと調和する高いシナジー状態が発生しつつある。高シナジーの未来には病気だって消滅する。暁の鐘は鳴る。少なくとも12月に入って、ハートの奥にある過去と未来が交差する場で、暁の鐘が、ちいさく、だが高らかに打ち響きはじめている。犬は東に向かい遠吠えをはじめた。
2020年11月10日

夕食は、教室でつくったであろうサラダをいただいた。メインのお皿がとくにすごかった。茹でたか蒸したかした紫芋に、コリアンダー、クミン、チリ、塩麹(かな?)を混ぜてペーストにしてある。これを、皿の上に薄くしく。そのペーストの上に、ベビーリーフが山盛り。あと塩麹でつけたローのままのブロッコリーやカリフラワー、ちいさく切った柿、アマランサス、蒸した紫芋のかけら、などなどがどわわわっとケチケチすることなく、しかしうつくしく盛りつけてある。海苔ものる。すだちをたっぷりかける。あのね、これがね、もうね、信じられないくらいおいしいのであります。紫芋のペーストがドレッシング的な役割になるのだが、チリが効いてておいしいの。感動した。ささくんは、いちじくものせたかったみたいだった。食べだすと止まらない。久しぶりに食べたささくんの味。食べたことのない味。いろいろな味がする。なんというか、こう、自分の中の何かがぱちーんと弾ける味なのです。目醒める味。ただもうひたすらにもりもりと食べ続けた。おなじみ、大根麺を甘酒にひたして食べるローの料理とか、スムージーとかもあって、すっかりお腹がいっぱいになった。ケータリングのカレーはまた淡路島にきたらあらためて食べに行こう。ちなつさんがつくったけんちん汁は、お鍋の中でお豆腐が汁を吸ってぱんぱんになっていた。その様子がいかにも家みたいで、ちなつさんはみんなのおかあさんだとあらわしているようで、かたわらにはめちゃめちゃ成熟してるおとうさんのけんちゃんがいて、実家に帰ったみたいに心底安心した。大人になるって、本当にたのしい。
2020年11月10日

京都で寝る前も、まだ次の日どうするか決めていたわけではなかったけれど、起きたらやはり「今日は淡路島へ行くのだ」とはっきりした気持ちがあらわれた。出発してからはじめてどいちなつさんに電話。ちなつさんの名が光るのを見ていたら、ちなつさんはこれだけでわたしが淡路島へ向かっているとわかるだろうなと直感した(実際そうだった)。ほどなくしてちなつさんから折り返し電話がかかる。この日料理教室のゲスト講師をしているささたくやくんには内緒で、教室後、アトリエにうかがうことなどをささっと算段する。前日にジュン・サンたちに教えてもらっていたとおり、神戸あたり? 神戸の手前なのか? むちゃくちゃ混んだ。我々、寝坊したのである。それでも淡路島には予定より1時間半前くらいに到着して福ちゃんは、暴風の中、海岸でビーチグラスを拾った。これは、福ちゃんのかなり重要な趣味のひとつである。わたしはやはり暴風でゆさゆさと揺れる車の中でうとうとしたりメールを打ったりする。外では、ジェットスキー(?)の大会が行われていて、でも暴風のため休止している、みたいな雰囲気だった。大勢の愛好家が行き来している。バイク好きとサーフィン好きがまざったみたいな風貌の人が多い。教室がちょうど終わる頃、アトリエに到着した。ささくんとは約1年ぶり。ちなつさんけんちゃんとも数か月ぶり。でも昨日まで会っていたみたいな気持ちになる。けんちゃんなんてほとんど話したことないのに、けんちゃんと呼んでいるわたしがいるほどだ。自然に夕食を一緒にいただくことになる。目の前で、ささくんとちなつさんがつくってくれる。じっと考えながら料理をするささくんの頭には、いまごろあの料理の構造をしめすキューブが浮かんでいるのかしらんと思う。確かに味を構築していっている感じが、つくっている様子からもうかがえる。
2020年11月2日

もうお夕飯を食べたのだからまたどこかへ行くというのもヘンだけれど、京都に来たのは、友人知人読者さんの各展示に対するあらゆる不義理をおして、唯一時間がとれたジュン・サンの初個展の展示を見に来たからで、ジュン・サン展の流れでそりゃ飲みに行きましょうとなるに決まっていた。28年前からの続きで50歳で初個展。初日に絵が間に合っていなかったけれど、でも展示会場で絵を描き続け(!)、わたしが到着した最終日前日には壁にはずらっと絵があり、中央にしつらえたテーブルには描きかけの絵もまだあった。会場では佐野元春の「YOUNG BLOODS」が流れていた。テーブルには食べかけのチョコレートが散らかっていた。机の下には壊れた内部をあらわにした年代物のノートパソコンが、それもまた現代アートである、みたいにして横たわっていた。もう1週間近くジュン・サンは、銭湯に通いながら寝泊まりしているという。ジュン・サンが教えてくれた店は、地元の人でもなかなかたどり着けなそうな、ご夫妻が営むお寿司屋さんだった。タクシーの運転手さんに行き先を伝えると「あのお店まだありますのん」と3回は感心していった。お店には、テーブルがふたつあって、到着する直前までカウンターもわたしたちの予約席をのぞいて満席だった。おくさんであろう女性が、おすしのお持ち帰りの包みをそれはきれいに包んでいた。きっちりとお寿司がつまった中身をのぞきたくなった。背後で話している男性たちは、関西でしか見ない顔つきで、同じくらい見たくなってしまう。これまで見たことがない顔なのだ。顔が小ぶりで、どうもはっきりしすぎている。あんな顔見たことない。発声からして違う。すごく溌剌としている。ビールで乾杯したあとは、めいめい好きなものを選んでいった。まずシマアジを食べた。ネタが分厚くて、口のなかでどわっとおいしさが広がる。イワシも穴キュウ巻も全部目がまるくなるほどおいしい。ジュン・サンの友だちは、わたしではなくて福ちゃんなのに、福ちゃんを飛ばしてどういうわけだかずっとわたしの顔を見て話している。ジュン・サンの潤んだ目を見て、おいしいお寿司を食べていたら、自分が今どこにいて何をしていて誰なのかわからなくなってきた。だいたいどうしてわたしの逆隣には、ジュン・サンが最初にこの店に連れてきてもらった女性が座っているのだろうか。どうして「みれいさんは何の仕事にしている人ですかクイズ」がはじまっているのだろうか。そんな頃に、二人の友人がおいついて5人でカウンターに並んだ。おくさんは、わたしたちに全員の背中に、同じまんまるのステッチがはいっているのを見て、いぶかしげだった。「オカルトとかいわんといてよ」って、おくさんはテーブルを拭きながらいった。ふと店内の壁を見上げたら、「萬丸」って書いてある。まんまるな店にまんまるステッチの5人が集合してるのは、オカルトっていうよりも、むしろ完全さのメタファだと感じた。ヤングブラッズ、肯定のメロディ。話すうちにジュン・サンとわたしは同じ年の1月と12月生まれであることがわかった。「冷たい夜にさようなら」。佐野元春さんの声を思い出しながら、路地裏の若者たちの喧騒に紛れて帰途につく。50歳ってほんとうに、なんというか、20歳みたいなんだなあと思いはじめていた。
◎ 佐野元春「YOUNG BLOODS」
https://www.youtube.com/watch?v=eDPj3KmxBPg
◎ ジュン・サン
https://www.instagram.com/jun__than/
◎ ジュン・サンにまつわるもうひとつのエッセイは、「mmbsほころんだ、ほころんだよ通信2020冬−2021新春」(購入してくださったかたにお配りしているzine)に掲載予定です
2020年10月26日

急遽京都へ行くことになった。フクチャンはもうずっと前から淡路島へ行きたいし、この金曜日と土曜日ならば、その両方になんとか行けそうだと直前に決めて西へ向かった。美濃から京都は車で2時間半くらいかなあ。関ヶ原を超えたあたりで、もうここは東海圏ではないと感じる。きっとことばも違うはず。滞在中は期せずしておいしいものばかり食べることができた。「菜食 光兎舎」は、ランチ営業だけなのだけれど、いろいろ事情があっておなかがペコペコで営業外だったのだけれど、特別にゆうきくんがまかないごはん的なごはんを少しだけ出してくれた。その日のランチメニューでもあったきのことなんだったかな、何かを合わせたポタージュをまず出してくださって、濃厚な秋の味のなかに淡い酸味がほどよく感じられて、度肝を抜かれた。繊細で、でも陽気で、たのしい味だった。見た目も京都らしいうつくしさで彩られて、本当に感心してしまう。お惣菜の中にれんこんのきんぴらにもびっくりした。この日はパセリであえられていたのだが、通常はディルであえるのですって。あと水にさらさないっていってた(わたしもそういう方向性が好み)。歯ごたえがあり、お醤油とみりんとお酒と唐辛子で煮た正統派の味ながら、パセリの香りとあいまって、びっくりするほどおいしい。味を、つい、二度見する感じ。自分でもぜひつくってみよう。なますも玄米ご飯もなにもかもおいしい。京都ってなんてすてきな場所なんだ。ゆうきくんがつくりだす食の世界がさらに進化していてにまにましてしまう。ありそうでどこにもない、家庭で食べる自然の味が、こう、ブラッシュアップされて、でも、洗練されすぎない家庭的な控え目さとともに、にぎやかにわいわいと供される光の兎のお店なんであります。跳ねたくなりますね。近所のかたがたは、こんなお店があってとても幸運だ。
光兎舎
https://www.instagram.com/s.kousagisha/
2020年10月19日

日曜日の夕方、特に4時あたりってほかにはない時間帯だと思う。たとえばこの時間に電話で話せる相手、あるいは話したいと思う相手は、とくべつな相手という気がする。ちからが完全に抜けてしまっている時間。あいまいで、ぼんやりしていて、無意識が表面に出てしまうような。最大限にリラックスしているときといってもいい。だからといってここちいいわけでもない。少しへんな時間。安逸を貪るための時間といったらいいか。そうそう、プリミ恥部さんの「感謝」というエッセイの冒頭の一文、「曇り空、最近好きだ」というような気持ちといってもいい。まさに昨日はその時間(もちろん日曜日だ)に、プリミさんとトークライブがあって、公で、その(わたしにとっての)無意識の時間を共有することになったのもおもしろいと思ったのだけれど、まさに美濃は、この「感謝」のエッセイの冒頭みたいな曇り空で、突然寒くなっていて、つい数日前までTシャツだったのに、セーターを引っ張り出して着るような気温になっていた。沖縄にいるプリミさんのほうはといえば、こんがり日焼けして、今まで見たことがないような陽気さで画面の向こう側にいた。あかるい陽の中でmoriiyukoさんのオーナメントとともに、揺れて、さらなる脱力のなかで、あたらしい歌を歌っていた。プリミさんが、歌に出てくるピンクビーチを堪能する頃、わたしは、小屋にある薪ストーブの火を凝視していた。火はいくら見ていても見飽きない。薪が火とじゅうぶんに一体化して最高の状態になった瞬間を見るのが好き。薪にも春夏秋冬があり、薪じたいがとても極まる時間がある。そのとき、火そのものとなった薪をトングで叩くと、ぱあっと割れて銀河のようになる。星々が散り散りになる。こちらもついまぶしい気持ちになる。海岸のピンク色も、薪の火のほのおの朱色も、どこかでつながっていて、同じ暖色ならではの愛を享受しているかもしれない。ふと、日曜日の午後4時に電話で話していた、あのまどろんだ時間のことを思い出す。あの時間に話していたあの人たちは、今どこで何をしているんだろうか。でもどんな想像も、もう、こころに思い浮かばなくなってしまっていて、自分が、以前とはすっかり違う、あたらしい場所にきてしまっていることを知り愕然とした気持ちになったりもする。
2019年11月14日

c 松岡一哲
かあさん、
わたし
40だいもこうはんになっても
まだかわりつづけているのと
おおあめのひに
まったくたいようがみえないそらにむかって
うそぶいてみる
かわってかわってかわって
わたしはあいになってしまった
昨秋のことだ
あいになってしまったら
ぜんぶわかる
あいになってしまったら
さかいがなくなって
そうして同時に
かんぜんなるひとりきりになる
かんぜんにぜんぶとつながってる
そしてひとりなのやっぱり
あはは
おかしいね
いや まって
かなしいのかな
あらゆる感情という感情が
どんどんどんどん
背中の各所からとびだしていく
龍の背なに乗って
さよならわたし
こんにちはわたし
おおあめの向こうから
山がこちらをのぞいてる
山だって
おお
わたしじしんなのであった
2019年2月10日

からだごと感謝になって歩いていたら
きら
きら
きら
と空中で光がまたたくようになった
天使ですか?
霊界の視点はいつだって清(さや)か
2018年4月7日
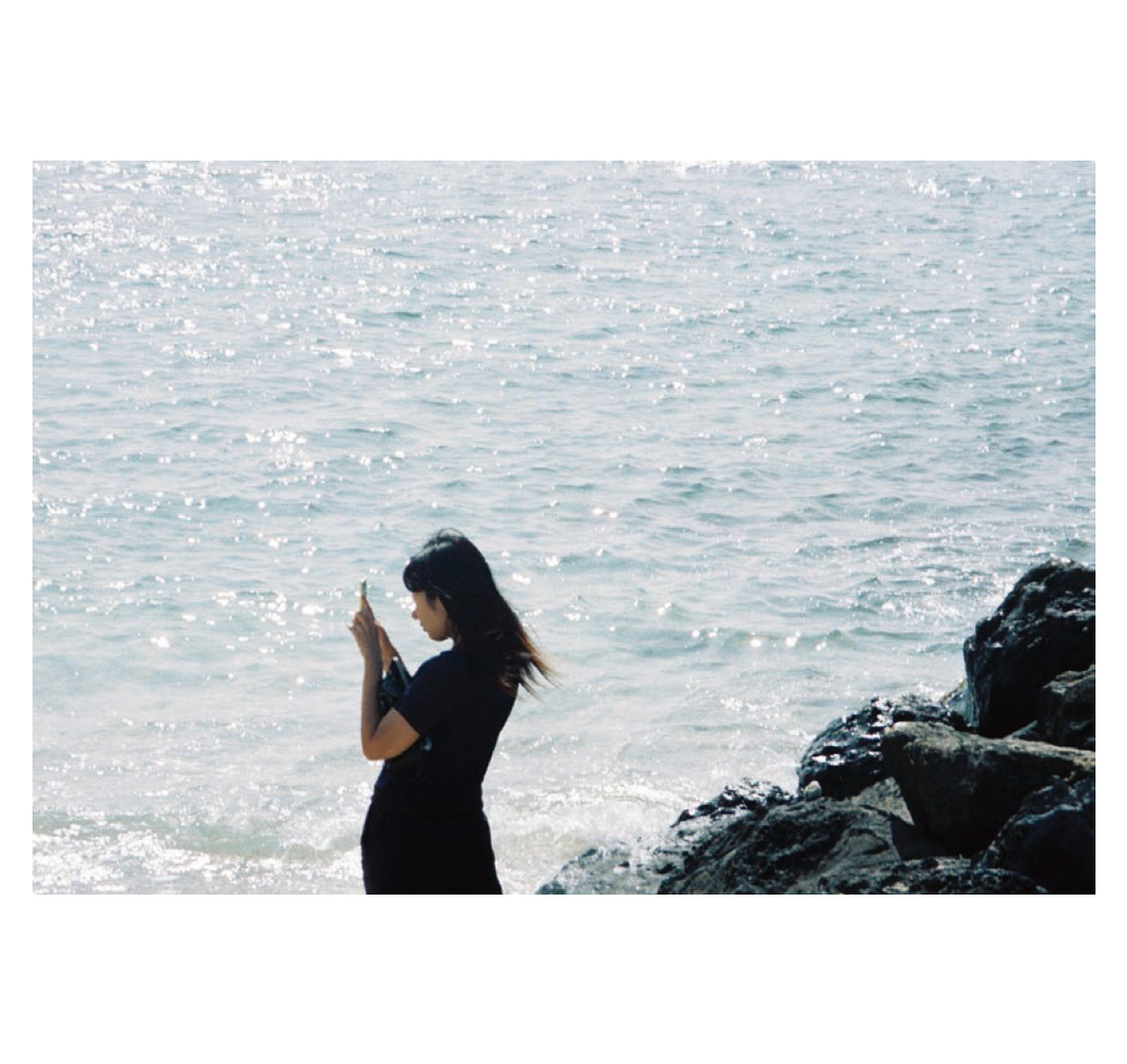
©Ittetsu Matsuoka
友だちが少し前にZAZEN BOYS をYou Tubeで見はじめたら止まらなくなってしまったという話を聞いて、「えー、それもう、何年か前に終わったブームだわ」と思っていたら、この春突然、同じ病気にかかってしまった。早この2日間、えんえん、ZAZENをYou Tubeで見続けている。COLD BEATとか。冷凍都市のど真ん中の、ね●500ページを超える写真集『マリイ』のリリースがいよいよ目前に迫り、胸の高まりを抑えられないのか。写真集『マリイ』について、松岡一哲くんという写真家について、語りたいことは山のようにあるのだけれど、なかなか語れない自分がいる。安易に語りたくなんかないとも思う。本当に優れた写真には、何をいってもことばなど陳腐なのだと今回ほとほと思い知らされたからだ。ことばなどで語れないものがあるから、写真家は写真を撮影するのでしょう? だとしたらことばで何かいう必要などあるのだろうか? ●若いころある一部の音楽誌を除いて音楽について書かれたものを読むのがつらかった。音楽が言語化するとは、ほとんどの場合が無駄なことだと感じる。ライターの過剰な自我と承認欲求で溢れた原稿をどう読めばよいのか。ライナーノーツも好きじゃなかったし。音楽は聴けばいいだけのことだし、写真も観ればいいだけのことだって思う。ことばにならないから、音楽は存在し、写真というものが在るのでしょう。一哲くんの写真が、今回、もう、いやというほど、そのことをわたしに突きつけた。500ページ、何度観てもページをめくる手を止めることができない。佐々木暁さんが信じられない精度で一哲くんを、マリイを、編んだ。見開きごとの完成度はただならぬことになっている。一哲と暁と、そしてこの二人をこんなにしてしまうマリイって、もう、いったい、なんなんだよ! 写真集のオファー時に暁さんが地下深い暗闇で泣き、初校ではわたしが都立大学で号泣した。昨年六本木のタカ・イシイギャラリーでルイジ・ギッリを観たら、まったくもって、一哲くんはこの系譜にある芸術を、いや、これ以上の芸術をつくってるんじゃんと頰が紅潮した。わたしは、この数年間、写真という芸術と対峙した。とんでもない写真集ができてしまった。
2018年3月29日

わたしは、なんだけれど、ことさら声高に、〜を愛しているって、すきであればあるほどいいたくないたちだな。この土地、この環境、たとえば市とか県とか、ときには国っていうくくりになるこの場をわたしは、わざわざ声をあげなくともあたりまえに愛しているし、土地のウニヒピリや精霊たちだって、わたしの気持ちをすごく感じているもののように思う。愛しているって、どういう関係であれ、そうやってそっとうちうちで交換される、かつ通じあう何かなんではないかなと思っている。「おしどり夫婦」の大半が仮面夫婦であるように、逆に本物の夫婦は、きわめて無に近い目立たないものなんだと思う。あえて仲がいいとか、愛しているとか、その「かたち」を話題にのぼらせなくてはならないというのは、不安感があったりなんらかの弱気から起こるものなんじゃないのかな。愛国とか愛県とか愛市とかいわなくたって……たとえば愛犬家なんて名乗らなくたって犬のこと好きだし。愛し合っているふたりというのは、目と目でみつめあえば、ことばなんかなくたって充分にわかるものだと思っている。わたしと土地や国との関係も、ほんとうに、まったく同じなのだと思っている。こんなことをわざわざいいたくもないけれど、でもなんか、言語化する必要がある気になって、書きました。久しぶりに。
2017年9月2日

バッハのフランス組曲アルモンドについて、このように述べようと思っていた。人生の序章、これから始まると言わんばかりの高揚感。小川のような流れのある調べ。すべてこの美濃での生活を象徴するかのようである。それでいて、1曲の中に、いきようようとしたやる気、期待、ちょっとしたつまづき、やり直し、仕切り直し、問題の発生、困難、挑戦、挑戦、忍耐、忍耐からの夜明け、一旦来る許し、変容、変容から、いきなり天使の世界へ。目に見えない世界は、この目に見える世界の大元で物質界はただ単に生き写しに過ぎない。天空で何が起こっているか。そこにもドラマがあって、かつそこには許ししかないという事実、許し、許し、最後においては許しだけになるという、まさに人生と、死んでからの人生みたいなものがたった短い1曲に詰まっている。弾き方は、まるでできないけれど、グレン・グールドみたいにはやく(本当はスタッカートだらけで弾いてみたかった!)弾いたほうがノれることが本番前々日にわかって挑戦だっだけれど、できる限り早く弾いた。そもそもピアノを習い直そうと決めたのは、岐阜でN響の演奏&チャイコフスキーのピアノコンチェルトを聴いたことがきっかけだった。あの時わたしは、死んだばかりの母とはっきり対話をした。具体的な助言まで降りてきた。音楽というのは、天につながる通路をいとも簡単につくるのだと驚愕した。今回発表会でバッハを弾いたら、やはり、母を思い出した人が会場におり、少しは成功したといえるのだろうか。なお、先生と連弾したエリック・サティのピカデリーは、焼肉屋さんでじゅうじゅう何かを焼いているかのような、もうもう煙が立つような演奏だった。会場となった夕暮れの美濃保育園も最高だった。わたしにピアノがあってよかったです。
2017年6月14日

この歳になって発表会なるものに出演することになるとは誰が想像しただろうか? 先生は春に、「みれいさんにはバッハがいいと思う」といった。わたしもそれがいいと思った。バッハは、どの作曲家とも違う陶酔感、高揚感、無に至る感じがすごい。自動演奏みたいになってくる。天と地と私だけになる。バッハの中でフランス組曲からある曲を選んだ。練習しはじめたら、もう止まらない。すぐに続けたくなってしまって何度も何度も何度も何度もアホみたいにループしてしまう。練習が練習でなくなってただもう指が止まらない。赤い靴はいた少女状態。くるくると踊らされる。それだけではない。朝起きれば起きた瞬間から昨夜練習したフレーズが頭で鳴り続ける。歩いていても食べていてもフランス組曲。寝て覚めてもフランス組曲。左手の音の流れ、主なメロディライン、そして中間のラインの音たち……。バッハ、一体、アンタ、どうなってんだ⁉︎ 人生のはじまり、高揚、事件、落胆、許し、何もかもが音符にのっている。そこに自分自身が入り込むと陶酔となる。これはもはや麻薬である。依存症である。フランス組曲中毒である。猫は私が心配になったのか、バッハを弾きはじめると必ず、傍らで黙って番をするようになった。発表会は、岐阜にて、夏の夜に小学生を中心にとり行われる。
2017年5月19日

土を耕す、苗を植える、種をまく、たけのこ掘り、わらび採取、ジェフ・バックリー大音量でたけのこの下茹で、わらびも下茹で、米ぬか、木灰、唐辛子すべて自家製とわかりひとりほくそ笑む、iaiの服はひとつの事件である、わたしたちは事件の目撃者である、革命はもう起こってしまった、山菜の天ぷら、傷跡はもう少しで消えそう、川辺でよもぎ採り、暑い、帽子の中によもぎを入れる、山へ移動、すでにふらふらだし、倍音のうぐいすによるねぎらい、一体どれだけの太い声なんだ、たけのこが見つかる、父に報告、父Kトラで向かう、父掘る、3つあった、よもぎを水洗い、それをはらう時によもぎシャワーになる、よもぎシャワーを顔に浴びる、ツバメ、ツバメ、ツバメ、セリを水辺に見つけた、セリが本物のセリか隣のおばあちゃんに確認、本物だった、エンドウをいただく、へびいちご採取、へびいちごのチンキづくり、ドクダミの若い葉採取、ドクダミのチンキづくり、キハダと甘草の焼酎漬けづくり、エゴマのしょうゆ漬けづくり、種をまく、水をやる、暑い、振り返ればアスパラガス、ディルとコリアンダーはいつだって風に揺れている、増山たづ子写真集見て泣きながら眠る、徳山村はうつくしかった、徳山村の人々も、バッハ、フランス組曲ドイツ風に、突然の悲劇それが人生だ、しかしいつしか夜明けもやって来るそれも人生だ、グレン・グールドはなぜ右手と左手を独立して弾けたのか、右手と左手がいつの間にかお互いを依存しあい境界線がなくなってしまう、バッハを弾く右手と左手にこそみの虫革命を、美食家の玄米リゾットは独立の味、おにぎりは3種握る、田んぼの畦を見守る、カエルはいつだって逃げる、自生のイタリアンパセリとコリアンダー発見、自生のディルは大量に、立ち話、立ち話、立ち話、立ち話、立ち話、近所の駐車場ではイチゴが自生、どうなってんだ?(北の国からで木谷涼子先生に純が言うような発音で)、種まきの上には藁を敷く、お茶っぱの採取法とモミモミ法を明日90歳の隣人から教わることになった、次のことをみんな考えてるね、塩むすびがいちばんおいしいことの秘密は果たして加齢なのか、近所のおばあさんにディルをプレゼントした夜、永遠に続きそうだわこの黄金週間
2017年2月20日

神は外側にいるのではない
神はわたしの内にある
内にあって輝いている
わたしがそのことを忘れているときでさえ
サックスのブー
トランペットのパオー
ギターにどれだけエフェクターつけたって
神はいる
そこかしこに 空気の粒子のツブツブに
時にプンクトゥムかのごとく
投げられた武闘家の背中(せな)にも
雨でもない
かといって雪でもない
空から光が舞い降りる中(なんと山あいの町では光が降る日があるのだ!)
ピアノ教室へとうつむいて歩きながら
我が世の神を悟る
誰だって勢いよく神である と
誰だって勢いよく神である と たびたび